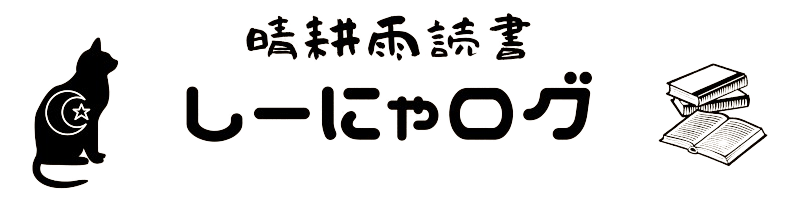ーー同じようで全然ちがう、高炭素資材との付き合い方ーー

畑の土がカチカチで雨が降ると数日入れないほどに水はけも悪い。
粘土質の固い土を見ると、つい「何か軽いものを混ぜてフカフカにしたい」と考えがちです。
そのとき候補に上がるのが、「おがくず」や「生の籾殻」。見た目も軽くてかさがあり、いかにも土を柔らかくしてくれそうな資材です。
しかし、使い方を間違えると、「フカフカになったけど作物が育たない」という本末転倒な結果にもなり得ます。
ここでは、おがくずと籾殻の違いと、粘土質改良にどう活かすべきかを整理してみます。
おがくずも籾殻も「高炭素資材」という点では同類
おがくずも生の籾殻も、どちらも
炭素が多く、窒素が少ない「高炭素資材」に分類されます。
俗に言う高C/N比資材ですね。
このタイプの資材には、共通した特徴があります。
- 土に混ぜると一時的にフカッと軽く見える
- しかし、微生物がそれを分解するときに、足りない窒素を土から奪う
- 結果として、作物が窒素不足(窒素飢餓)に陥りやすい
つまり、
「おがくずなら粘土改良になる」
「籾殻なら入れ放題でも安全」
という考え方は、どちらも危険です。
どちらも“窒素を喰らう資材”であることを前提に扱う必要があります。
「おがくず」と「生籾殻」のちがい


それではこの2つの高炭素資材にはどのような違いがあるのでしょうか。
現場感覚も含めて、次のように整理できます。
窒素飢餓の強さ
- おがくず
- 炭素:窒素の比率が非常に高い
- 微生物が分解を始めると、かなり強く窒素を持っていく
- 生のまま大量に鋤き込むと、土壌中の窒素飢餓により作物の葉色が抜け、生育停滞が起こりやすくなる
- 生籾殻
- こちらも高炭素ですが、おがくずほど極端ではないことが多い
- 現場では「おがくずよりはトラブルが少ない」という印象が強い
同じ量を入れた場合
窒素飢餓のリスクは「おがくず > 生籾殻」と考えた方が安全です。
ただし、籾殻でも大量にすき込めば普通に窒素不足は起きる、と見ておくべきです。
土を「軽くする力」とその持続性
- 生籾殻
- ボート状の殻で、軽くてかさがある
- 土に混ざると大きめのすき間をつくりやすく、排水性・通気性の改善に寄与する
- ケイ酸やリグニンが多く、分解がとても遅い
- その分、物理的な「かさ」が数年単位の長期で残りやすい
- おがくず
- 細かいチップや粉状で、分解が進みやすい
- 数年たつと形が崩れ、最初の「ふかふか感」はあまり残らない
- 混ぜ方によっては、かえってすき間が潰れてしまうこともある
粘土質改善という一点に絞れば、
同じ“生”で使うなら、おがくずより生籾殻のほうがまだ土を軽くしやすい
といえます。
粘土質改良の「主役」と「脇役」を間違えない
粘土質の根本的な改良を考える場合、
実はおがくずも生籾殻も“主役”ではありません。
粘土改良の主役にすべきもの
- 牛ふん堆肥・バーク堆肥などの完熟堆肥を、毎年少しずつ継続投入
- 排水性が悪い圃場では、
- 明渠・暗渠などの排水改善
- 高畝にして、根域を水から逃がす
- 石灰・苦土石灰などによる、
- pH調整
- 団粒構造(つぶつぶの土)をつくる土づくり
このあたりが、粘土質改善の本丸です。
一方、おがくずや生籾殻はあくまで「脇役の資材」と考えた方が安全です。
おがくず・籾殻をどう活かすか

まずは「堆肥化してから使う」のが基本線
それではあくまで「脇役」の資材を有効的に活用するにはどうすればいいのか。
おがくず・籾殻のどちらに対しても、一番無難な使い方は
窒素源(家畜ふん・化成肥料・尿素など)を混ぜて堆肥化してから、土に入れる
という方法です。
- 山に積んで、水分を維持しながら数ヶ月寝かせる
- ときどき切り返してやると発酵が進みやすい
- 黒っぽくなり、おがくずや籾殻の形が崩れてきたら“ほぼ堆肥”
こうしておくことで、
という、扱いやすい資材に変えることができます。
「土に混ぜない使い方」を選ぶ
どうしても生のまま使いたい場合は、土に混ぜず表面利用にとどめるのも一つの手です。
- 通路に敷いて、ぬかるみ・泥はね防止に
- 株元のマルチとして敷き、
- 雑草抑制
- 表面の固まり防止
この使い方であれば、
土中で一気に分解が進むわけではないので、窒素飢餓のリスクは比較的緩やかです。
粘土改良目的の「おすすめ順位」
粘土質の畑を改良する目的に限って、現場での使いやすさをざっくり並べると、次のようなイメージになります。
- 籾殻くん炭
- 窒素飢餓ほぼなし
- 物理性改善+pH緩和などの副次効果も
- 籾殻堆肥(籾殻+家畜ふん等で堆肥化したもの)
- 生籾殻(少量+窒素補正を前提)
- 生おがくず(できれば堆肥化前提。生の大量鋤き込みは避けたい)
同じ「高炭素資材」だが、扱いは慎重に

- おがくずも生籾殻も、土をフカフカに見せる一方で、窒素を食うリスクを持つ資材です。
- 「生のまま大量に混ぜれば粘土が改善する」という考え方は、どちらにもあてはまりません。
- 粘土質の根本改良は、
- 完熟堆肥の継続投入
- 排水改善
- 適切な石灰資材
が主役であり、おがくず・籾殻は堆肥化してからサポート役として使うのが無難です。
改めてお伝えしますが、どうしても時間的都合や立地、場所の都合により生のまま投入する際は少量を鋤き込み、窒素資材も同時投入することをおすすめします。