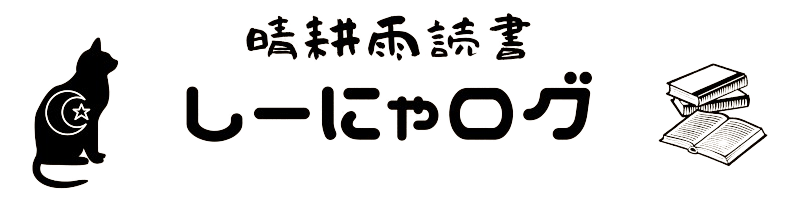雨のあと、畝の上を指でなぞったらツルッとして、乾くとパリッと割れる——そんな“薄いカサぶた”みたいな層ができると、水は染み込まず、表面が硬いため種子の発芽を妨げてしまいます。
でも多くの場合、播種直後のひと工夫と水の落とし方を変えるだけで防げます。
本記事では、現場で判断しやすい目安と、今日からできる対策を整理しました。

この現象はなに?“表面の薄い硬い層”ができる仕組み
- 雨滴やかん水の衝撃で土の粒が壊れ、細かい粒(シルト・粘土)が表面で詰まって、薄く硬い膜(クラスト)になります。
- その膜が水の入り口を塞ぎ、乾くとひび割れて、乾燥でさらに硬化して発芽・出芽が不揃いになります。
- とくに細かく耕し過ぎた直後、裸地で被覆がないと起きやすいです。
起こりやすい条件(思い当たる点は?)
起こりやすい条件
- 細かく砕きすぎた表層。
砕土が細かすぎて粉状になっている(ロータリの耕起し過ぎ) - 露出した裸地(残渣・マルチなし・敷きわら・不織布なし)
- 表土に有機物が少ない/団粒が脆い土
- シルト質~微細砂の多い土
- 灌水で大粒の水滴が落ちる散水(高い位置からのスプリンクラー等)
- ナトリウム過多(ソディック傾向)の圃場や水
典型的な症状
- 表面がサクッ→ガリッとする薄い硬膜
- 雨上がり後に水たまりが長く残る
- 出芽がまばら・割れ芽・苗の白化
- 乾くとひび割れ、湿るとぬめり
まずはここをチェック(現場でできる1分診断)
- 指爪テスト:表面2~5mmが爪で削りにくく、下層は柔らかい → クラスト化の可能性大
- 空き缶浸透テスト:底抜き缶を3cm埋め、200ml注水。5分以上水面が下がらない → 表面シール疑い、水の通り道が詰まり気味。
- 出芽差:覆土厚さが同じなのに、畝の高所と低所で出芽差が大きい → 表面流亡とクラスト併発の可能性
作物別のリスク感(目安)

クラスト化した土壌
種の小さい野菜は土を持ち上げられないので発芽不良になる可能性が・・・
- リスク大:ニンジン、ネギ、レタス、ホウレンソウ、ゴマ、コマツナなど小粒種子
- リスク中:ダイズ、コーン、エダマメ、ソルガム
- リスク小:ジャガイモ(塊茎)、バレイショ類・定植作物全般
小粒種子は覆土が薄い+出芽力が弱いため覆土1~1.5cm、鎮圧は軽くが基本です。
すぐ効く“応急処置”(播種後~出芽期)
- 軽い灌水で柔らかく→浅くほぐす
早朝か夕方に細かい霧状で湿らせ、レーキや中耕具で1~2mmだけ表皮を割る。深くやりすぎると種が露出します。 - ロータリーホー/ミニハロー(畑用の軽い鎖歯)で高速・浅掛け
出芽列を避け、畝肩~畝間をサッと。風乾前に。 - 行間だけ点滴または細霧
出芽線上に水膜を作らないよう畝間に点滴→表面張力が下がり、殻が割れやすくなります。 - 重ね播き(再播種)判断
播種後7~10日で発芽が3割未満なら硬い層を薄く削って部分追い播き。元肥過多なら浅く削ってから播き直します。
予防策(短期:播種~定植時の工夫)
- 砕土は“米粒~小豆大”で止める:パウダー状まで崩すと雨滴で膜化しやすくなり固まりやすいです。最後はレーキで軽く整地に留めます。
- 被覆で雨滴エネルギーを落とす:敷きわら・剪定枝チップ・バーク堆肥薄敷き(3~5mm)、不織布、紙マルチ、フィルムマルチ。
- 播種深さの最適化:小粒種子は1~1.5cmを維持。鎮圧ローラーは“軽く1回”。押しすぎるとシール化の下地に。
- 潅水方法の見直し:高所からの大粒散水は避け、低圧・細霧ノズルや点滴へ。
- 等高線方向の畝立て:表面流亡を抑え、細粒分の集積を減らします。
- 残渣を少し残す:全面清掃よりも、細かく刻んだ作物残渣を2~3割残す方が団粒が守られます。
根本対策(中期~長期:土づくり)
- 有機物で団粒を育てる:完熟堆肥・カバークロップ(ライ麦、エン麦、ヘアリーベッチ等)で表層の安定団粒を増やします。年に1回、乾物で1~2t/10a相当を継続。
- 過耕起の回避/不耕起・少耕起の導入:毎作ロータリ細砕より、条播部だけ浅耕に変更すると表層が安定します。
- 石膏(硬質石膏)やカルシウム資材:ソディック(Na過多)傾向が疑われる場合に有効。Caで分散した粘土を凝集させ、浸透と団粒安定を改善。施用は土壌・用水の分析結果を確認してから。
- 用水の見直し:井戸や灌漑水の電気伝導度(EC)・Na比が高いとシール化に拍車。可能なら雨水・低Na水を播種~出芽期に優先利用。
- 輪作で根を入れる:深根性カバークロップ(ソルガム、ライムギ)で表層~下層の連通孔を確保。
よくある“やりがち”ミス
季節のポイント(10月~11月)
- 秋雨前線・台風後はクラスト化が急増。播種は雨直後の泥面を避け、1~2日乾かしてから細霧で落ち着かせると◎。
- 冬作前の被覆資材とカバークロップ播種は、春のひび割れ予防に直結します。
早見表:原因→症状→対策
| 主因 | 見られる症状 | 速効策 | 根本策 |
|---|---|---|---|
| 細粉化した表層 | ツルツル後にひび割れ | 霧状潅水→浅耕で割る | 砕土を粗めに、残渣・被覆を活用 |
| 裸地・残渣なし | 雨跡に薄い硬膜 | 不織布/薄敷きマルチ | カバークロップ団粒強化 |
| 散水滴が大粒 | 雨後に水たまり | ノズル変更・点滴化 | かん水設計の見直し |
| Na過多・団粒弱 | 乾くとガチガチ | 軽くほぐす+細霧 | 分析の上石膏施用+有機物継続 |
作業チェックリスト(保存版)
まとめ
クラスト化は「雨滴の衝撃×脆い表層」が主因で、播種直後の管理でほぼ予防できます。万一発生しても、湿らせて浅く割るのが基本。長期的には有機物の投入・過耕起の回避・適切な潅水で“壊れにくい表土”を作ることが最善策です。
初心者の方は被覆とノズル見直しから、中級者はカバークロップ+点滴化や石膏(分析前提)まで検討してみてください。
中期的には有機物の継続投入と過耕起の回避で、そもそも固まりにくい表土を育てていきましょう。